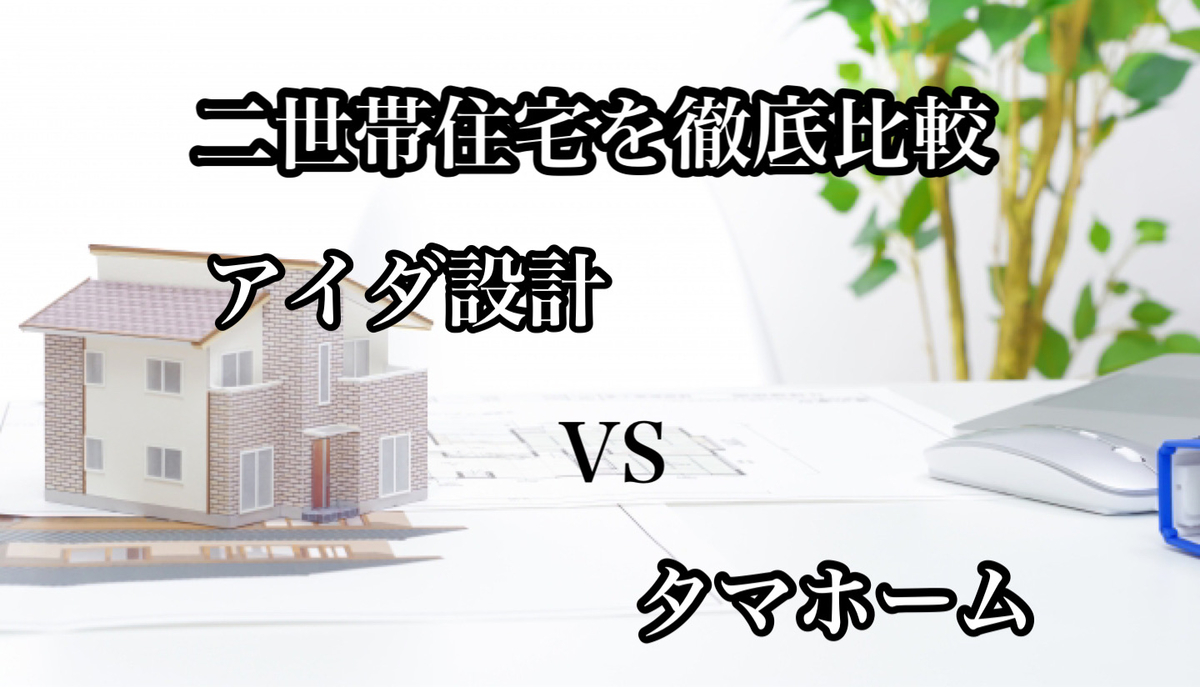この記事を読んで分かること☝
- 完全分離型 二世帯住宅の電気代(実例)
- 二世帯住宅の電気代が高くなる理由
- 二世帯住宅の電気代を抑える方法
「二世帯住宅の電気代は高いの?」という質問を時々見かけますが、実際、どうなのか具体的に回答している情報を見たことがありません。
そこで今回は、完全分離型 二世帯住宅である我が家の電気代を、公開することにします。
先に結論を書きますと、完全分離型 二世帯住宅の電気代は高いです。
なぜ、完全分離型 二世帯住宅の電気代が高くなるのか、メカニズムを考えながら、二世帯住宅の電気代を抑える方法を解説します。
毎月の電気代が高いというのは、家計の負担として大きいですから、これから二世帯住宅を検討される方は、ぜひ、最後まで読んでいただき、二世帯住宅 検討の参考にしてください。
2012年にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を新築。
二世帯住宅での生活(生活歴10年)しながら、最もローコストで理想の二世帯住宅が、どういうものなのか研究。
実際にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てた経験とその後の生活の経験を活かし、二世帯住宅の情報を発信中。
一男一女の父親。
- 二世帯住宅の光熱費は?
- 我が家(二世帯住宅)の基本情報
- 2022年度・2023年度・2024年度の電気代 実績
- 二世帯住宅の電気料金が高額となる理由
- 二世帯住宅は、電気の契約を分けるべき
- 二世帯住宅に「太陽光発電+蓄電池」のZEH住宅は必須
二世帯住宅の光熱費は?
光熱費には「電気」「ガス」「水道」の3種類があります。
私が二世帯住宅で暮らした十年間の光熱費平均は
- 電気:25,000~30,000円/1ヵ月
- ガス:15,000~20,000円/1ヵ月
- 水道:30,000~35,000円/2ヶ月
一見、水道代が高いように感じますが、これは2ヶ月分です。
この実績を見ていただいても分かる通り、光熱費で最も高額なのは、「電気」です。
そこでこの記事では、二世帯住宅の電気代に焦点を絞り、解説します。
二世帯住宅の水道代は、こちらの記事に詳しくまとめています。
我が家(二世帯住宅)の基本情報

ローコストハウスメーカーのタマホームで建てた完全分離型の二世帯住宅です。
完全分離型ですから水回りや家電製品は、すべて2つずつあります。
間取り
1階:2LDK(親世帯2人)
2階:3LDK(夫婦+中学生2人)
電気の契約(60アンペア)
完全分離型ですが、電気の契約は1つです。
2世帯分をまかなえるように60A(アンペア)の契約です。
10年間、暮らしていますが、これまでブレーカーが落ちて停電になったことはないので、完全分離型 二世帯住宅の場合、60A(アンペア)で十分です。
電力会社は、au電気です。(Pontaポイントに釣られました(^^;))
2022年度・2023年度・2024年度の電気代 実績
| 月 | 電気使用量 | 電気料金 |
|---|---|---|
| 1月 | 1,065kW | 32,272円 |
| 2月 | 944kW | 29,933円 |
| 3月 | 872kW | 28,622円 |
| 4月 | 731kW | 24,407円 |
| 5月 | 713kW | 24,215円 |
| 6月 | 829kW | 28,233円 |
| 7月 | 1,073kW | 37,517円 |
| 8月 | 1,134kW | 40,657円 |
| 9月 | 939kW | 35,022円 |
| 10月 | 692kW | 26,102円 |
| 11月 | 643kW | 26,368円 |
| 12月 | 811kW | 35,159円 |
| 月 | 電気使用量 | 電気料金 |
|---|---|---|
| 1月 | 905kW | 33,993円 |
| 2月 | 818kW | 30,942円 |
| 3月 | 738kW | 27,003円 |
| 4月 | 700kW | 24,960円 |
| 5月 | 720kW | 23,479円 |
| 6月 | 845kW | 26,361円 |
| 7月 | 1,171kW | 34,573円 |
| 8月 | 1,217kW | 33,922円 |
| 9月 | 1,042kW | 31,541円 |
| 10月 | 691kW | 20,685円 |
| 11月 | 732kW | 21,722円 |
| 12月 | 878kW | 25,852円 |
| 月 | 電気使用量 | 電気料金 |
|---|---|---|
| 1月 | 981kW | 28,957円 |
| 2月 | 811kW | 24,158円 |
| 3月 | 773kW | 23,435円 |
今年(2023年)に入ってから節電を頑張っており、昨年(2022年)と比較して電気の使用量は減少していますが、電気料金の値上げもあり、金額は思ったほど下がっていません。
電気代というのは、使用量が増えれば増えるほど、単価が上がっていくため、電力使用量の多い二世帯住宅ほど値上げの影響が大きいです。


主な家電製品
1階
- 冷蔵庫
- エアコン①
- エアコン②
- テレビ×2
- こたつ×2
2階
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- エアコン①
- エアコン②
- テレビ×3
- こたつ
特別な家電製品はないですが、夏場と冬場は、エアコンを使用するため、電気使用量が増加します。
ただ、テレビは全部で5台ですし、こたつも3台あるので、普通の家庭と比べると電気の使用量は大きくなります。当然ながら待機電力も大きいですね。
【二世帯住宅のエアコン選び】2階のLDKに使用するエアコンは消費電力で選ぶ - 大器晩成を信じて
二世帯住宅の2階は暑い(エアコンを使用する頻度が高い)
一戸建ての2階が暑いというのは分かりますが、二世帯住宅の2階はさらに暑いです。
実際に二世帯住宅で11年暮らしてみて、実感した暑くなる要因
- ロフト(勾配天井)
- 食洗器
想像以上に暑くなります。1階であれば、エアコンを使用する時期は6~9月ですが、二世帯住宅の2階は、5~10月までエアコンを使用する必要があります。それだけ電気代が高くなるということです。
【電気代の負担増!リビングが暑い原因は勾配天井のせい⁉】二世帯住宅で2階にLDKを造る際の注意点 - 大器晩成を信じて
二世帯住宅の電気料金が高額となる理由

我が家の利用している電力会社はau電気です。
【au電気の電気料金】
基本料金
- 10A⇒286円
- 20A⇒429円
- 30A⇒858円
- 40A⇒1,144円
- 50A⇒1,430円
- 60A⇒1,716円
1kWhあたりの電力量料金
- 0~120kWまで⇒21.03円
- 121kW~300kWまで⇒25.5円
- 301kW~⇒28.45円
電気料金というのは、アンペア数が大きければ大きい程、電気の利用量が多ければ多い程、単価が高くなっていく価格帯です。
二世帯住宅で1つの契約とした場合、明らかに電気料金の面でマイナス要素が大きいです。
理解するため、分かりやすく例をあげます。
600kWの電気使用量で60A(アンペア)の契約が1つの場合と30Aの契約が2つの場合の電気料金を比較してみます。
60A(アンペア)1つの契約
基本料金1,716円+電力量600kW×料金28.45円=18,786円
30A(アンペア)2つの契約
基本料金858円×2契約+電力量300kW×25.5円×2契約=17,016円
電力量料金の切り替わるkW数にもよりますが、二世帯住宅の場合、電気の契約を世帯毎に分けた方が、金額を抑えることができます。

二世帯住宅は、電気の契約を分けるべき
完全分離型の二世帯住宅であれば、家を新築する段階で、電気の契約は2つに分けることがオススメです。
理由は
- 電気料金を抑えるため
- 電気料金の支払い割合で揉めないため
上記で説明させていただいた通り、料金面において電気の契約は世帯毎に分けた方が良いです。
また、二世帯住宅の場合、親世帯と子世帯とで電気代の支払い割合が原因で揉めることも考えられるため、契約を分けるということは、揉め事を事前に防ぐという意味合いもあります。
私は二世帯住宅で10年暮らしていますが、電気代が高くなると親世帯と子世帯で必ず揉め事が発生します。これは必ずです。
毎月毎月、電気代のことで揉めていては疲れてしまいます。
二世帯住宅に「太陽光発電+蓄電池」のZEH住宅は必須

私が二世帯住宅を建てた時は、太陽光発電について真剣に考えることはなかったですが、10年暮らしてみて、二世帯住宅の電気料金の高さを身をもって知りました。
その私から一言
完全分離型の二世帯住宅に太陽光発電は必須です。
これは声を大にして言いたいですね。
⇒【2024年はZEH住宅の需要が高まる】ローコストハウスメーカー2社のおすすめZEH住宅
最近は、高断熱・高気密・省エネのZEH住宅が普及しており、各ハウスメーカーも太陽光発電を標準装備している住宅を発売しています。また、ZEH住宅は、断熱性能も高く夏や冬など、空調の電気料金を抑えることができます。
下のグラフは、ZEH住宅と一般の木造住宅の室温比較グラフです。
ZEH住宅では、エアコンを停止したあとの温度変化が少なく、省エネルギー住宅と分かります。

(出典:冬は暖かく、夏は涼しい住まい心も体も心地いい「快適ZEH」のすすめ|Column|ホームクラブ(homeclub)|住まいづくり応援ポータルサイト|ミサワホーム|Home Club)
イニシャルコストの問題もあるとは思いますが、それよりも暮らし始めてからの光熱費の方が大きな問題になる可能性があります。
太陽光発電というと売電価格を気にされる方が多いですが、二世帯住宅の場合は、太陽光発電の電力を蓄電池に溜めて、自家利用することが目的です。
<こどもみらい住宅支援事業について>
ZEH住宅の取得について、一定の条件を満たしていると助成金を受けることができます。
- 18歳未満の子供を有する子育て世帯
- 夫婦のいずれかが39歳以下の若夫婦世帯
で延床面積50㎡以上のZEH住宅や長期優良住宅を新築する場合、最大100万円の助成金を受けることができます。
これから二世帯住宅を検討される方は、ぜひ、電気料金にも目を向けて、後悔のない二世帯住宅を建ててください。それでは、今回の記事はこれで終わりです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
二世帯住宅をご検討の方にオススメ記事を2つ紹介させていただきます。ぜひ、読んでみてください。