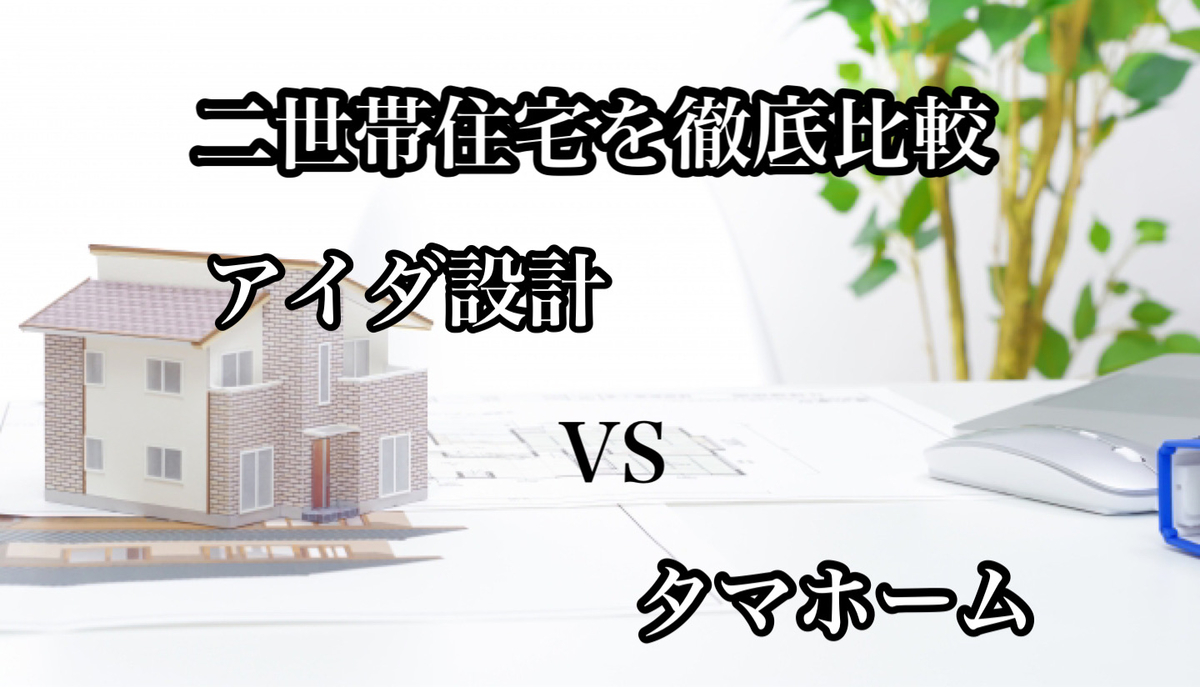この記事を読んで分かること☝
- 新築価格 値上のメカニズム
- タマホームの原価率
- タマホームの適正な値上幅
- タマホーム営業マンの営業トーク対策
昨年から家を新築するために必要な木材や住宅機器の値上がりが止まりません。その影響で住宅価格も値上げをしていますが、「その値上げ幅、適正ですか?」というのが、この記事の趣旨です。
要するに、「必要以上に値上げしていませんか?」ということです。
当然ですが、消費者が新築の原価を確認することはできませんので、実際のところは分かりません。
ただ、ハウスメーカーの決算書を分析すると、ある一定の値上げ幅という基準を見つけることができます。その基準をもとにハウスメーカーの営業マンと話しをできれば、必要以上に値上げされることを防ぐことができます。
家づくり中の方には、営業マンの「来月の契約だと○○%値上がりしますよ」というトークに惑わされないためにも、最後まで読んでいただきた内容です。
2012年にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を新築。
二世帯住宅での生活(生活歴10年)しながら、最もローコストで理想の二世帯住宅が、どういうものなのか研究。
実際にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てた経験とその後の生活の経験を活かし、二世帯住宅の情報を発信中。
一男一女の父親。
- 一部の材料が値上がりしただけでは、家の価格は上がらない
- タマホームの原価率から適切な値上げ幅を分析する
- タマホームの値上げ率は何%が適正なのか
- タマホームのキャンペーンは本当にお得?
- タマホームの適正な値上げ幅 まとめ
一部の材料が値上がりしただけでは、家の価格は上がらない

家の新築には、多種多様の材料が使用されています。
- 材木
- コンクリート
- 石膏ボード
- 防音材
- 瓦
- フローリング
- 住宅機器(トイレ、キッチンなど)
- etc
これらの原価と作業費を足して、家の原価です。
家全体の原価に占める「それぞれ材料毎の割合」は分かりませんが、例えば、材木を例にあげます。
家一軒には、たくさんの材木が使用されていますが、それでも家全体の原価に対して、20%もないでしょう。
計算しやすいように、仮に材木の割合を10%とします。新築全体の原価を1,000万円と仮定しましょう。
この場合、材木の原価は、新築全体原価の10%である100万円です。
材木の原価が、10%値上がりした場合、110万円です。
だから、材木の原価が上がっただけであれば、1,010万円が家の原価になります。
でも、割と多くの営業マンが、材木の値段が10%上がっているので、家全体の価格が10%上がります、という説明をしています。
おかしいですよね。でもほとんどの人は疑問に思わないんです。
- 材木のみ10%値上げ⇒1,010万円
- 家全体を10%値上げ⇒1,100万円
という感じです。
実際には、現在、材木以外にもあらゆる物の原価があがっているので、一概に言えませんが、ハウスメーカーの営業マンと価格について話をする際は、こういった視点は持っておいた方が良いです。
【タマホームは決算月に契約しても特典はない】ハウスメーカーと契約するなら決算月の3~4ヵ月前がおすすめ - 大器晩成を信じて
「原価があがったから住宅価格も上がります」という営業マンの言葉を単純に信じてはダメですね
タマホームの原価率から適切な値上げ幅を分析する

| 売上高 | 売上原価 | 原価率 | |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 167,915 | 126,701 | 75.5% |
| 2019年 | 186,874 | 140,873 | 75.4% |
| 2020年 | 209,207 | 159,269 | 76.1% |
| 2021年 | 218,092 | 165,872 | 76.1% |
| 2022年 | 240,760 | 185,502 | 77.0% |
| 2023年(第三四半期) | 173,853 | 132,459 | 76.1% |
上記表は、2018~2023年の売上高と原価、原価率をまとたものです。
2018年から2022年まで原価率が上昇しており、これは原材料費(木材など)の高騰によるものと推察されます。
2023年度は途中(第三四半期)までですが、原価率を2022年度より1%下げることができており、タマホームの売上で考えると、原価率が1%下がると単純に利益が30~40億円ほど増加します。
つまり、2023年度の期末まで、今の原価率を維持できれば、タマホームの利益はかなり上乗せされるということです。
2022年⇒2023年にかけて、原価率を抑えることができた要因は、材料の原価が下がったという動きはないので、普通に住宅の販売価格の値上げだと考えられます。
少なくとも2022年から2023年にかけて、1%以上の値上げをしていると想定されます。
例えば、3,000万円の住宅であれば、3,030万円で販売するということですね。
※計算式
仮に2022年も75%の原価率を維持できたらどうなっていたのか、シミュレーションしてみます。
2022年の数字は
売上高240,760ー売上原価185,502=利益55,258
<原価率77%>
単位が百万円ですから、552億5800万円の利益です。
仮に原価率を75%とすると
売上高240,760-売上原価180,570=利益60,190
601億9000万円の利益となります。
その差額、約50億円です。
こういう状況ですから、当然タマホームも値上げしようと努力するわけです。
原価率の上昇は、会社の経営を圧迫するので適正な原価率を維持するのは大切と思いますが、必要以上な値上げには要注意ですね。
タマホームの値上げ率は何%が適正なのか

ここ3年間は、原価率が76%、77%と上昇していますが、その前の2年間は、75%台ですから、タマホームの原価率の基準は75%というのが一つの基準ですね。
2022年⇒2023年にかけて、原価率が約1%改善しているので、値上げ幅としてあと1~2%値上げすると75%の原価率になります。
ですから今後も1~2%の値上げの可能性はあるということですね。
タマホームの場合、従来販売価格に対して、1~2%の値上げがあれば、適正な原価率となり、十分に利益を確保できる。
一方、これ以上の値上げ幅であれば、それは上げすぎ。
- 3~5%の値上げ⇒仕方ない値上げ
- 6~10%の値上げ⇒上げすぎ
タマホームの適正な値上げ幅は、3~5%ということを念頭において打合せを行ってください。
※これ以上の値上げ率の場合、しっかり説明を求めてくださいね。
営業マンに数年前と比較して、いくらくらい値上げしたのか確認してみるのも良いですね。値上げ幅が大き過ぎる場合はその営業マンは信頼できない可能性もあります。
タマホームのキャンペーンは本当にお得?
タマホームは、年中○○フェア 来場者に10,000円分のクオカード進呈という企画をやっていますが、それとは別に期末キャンペーンや決算キャンペーンを実施したりします。そのほか、○○月契約者に100万円分のオプションプレゼントなどですね。
実はこれらに使われる費用は、年間の販売促進費として予算計上されているものがほとんどです。
その販売促進費も考えて、家の価格は設定されており、その結果、タマホームは適正の利益を確保できているわけです。タマホームがお客さんのために身を削っているわけではないですよ。
キャンペーンをやっていない時に契約したら何もないかといえば、そんなことはないです。サービス品として、機器をつけたり、グレードアップしてくれたりします。
私の経験を書かせていただくと、タマホームで契約した時、前月までに契約していれば、100万円分のオプションプレゼントでした。「もったいなかったなぁ」と私も悔やんでいましたが、実際には100万円以上のオプションをサービス品としてつけてもらいました。床暖房やカップボードなどですね。
ここで何が言いたいかというとキャンペーンという言葉に惑わされてはいけないということですね。
タマホームの営業マンの特徴はこちらの記事でまとめていますので、読んでみてください。
ハウスメーカーの営業マンは契約を急ぐ傾向にあるので、おいしい話を持ち掛けられた時は、一呼吸をおいて「本当に得なのか」見極めることが大切です。
<ローコストハウスメーカーで新築をご検討の方へ>
ローコストハウスメーカーで検討するなら、予算に合わせて3つの選択肢があるアイダ設計を候補に入れてみてはいかがでしょうか。
というのも、ここ数年のタマホームは、会社規模が大きくなったせいか、以前ほどのコストメリットがなくなっています。
比較対象のない中で契約してしてしまうとあとで「他のハウスメーカーならどうだったのだろう」と後悔しかねないです。昔と違い相見積を取るのが当たり前の時代ですから検討してみてはいかがでしょうか。
- 999万円の注文住宅
- 888万円の規格住宅
- 分譲住宅

タマホームの適正な値上げ幅 まとめ
決算書の内容からタマホームの適正な値上げ幅を分析しました。実際には、建売やリフォーム事業の業績も入っているため、注文住宅だけの場合、多少前後する可能性はあります。
ただ、タマホームの場合、注文住宅事業がメインのため、この考え方で問題はありません。目安としては、十分に利用できます。
今の時期、どの業界も値上げですから、ハウスメーカーの営業マンも営業トークに「値上げ」というワードを頻繁に使ってくることでしょう。
その際、何となく話を聞いていたのでは、営業マンのペースになってしまいます。営業トークの真偽を見極めるためにも、基準を持っておいた方が良いと思い今回、値上げ率について、書かせていただきました。
最後にハウスメーカーの営業マンを責めて険悪な関係になってしまっては、あなたにとってデメリットしかありません。こういう原価率の知識も持ちながら、うまく信頼関係を築いて、満足度の高い家を建ててくださいね。
それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
下記記事は
- ローコストハウスメーカーで新築をご検討の方
- 予算をできる限り抑えたい方
によく読んでいただいています。特にこの記事を読んでくださった方は、家づくりに対して、真摯に向き合っている方だと思いますので、お役に立てる内容です。ぜひ読んでみてください。