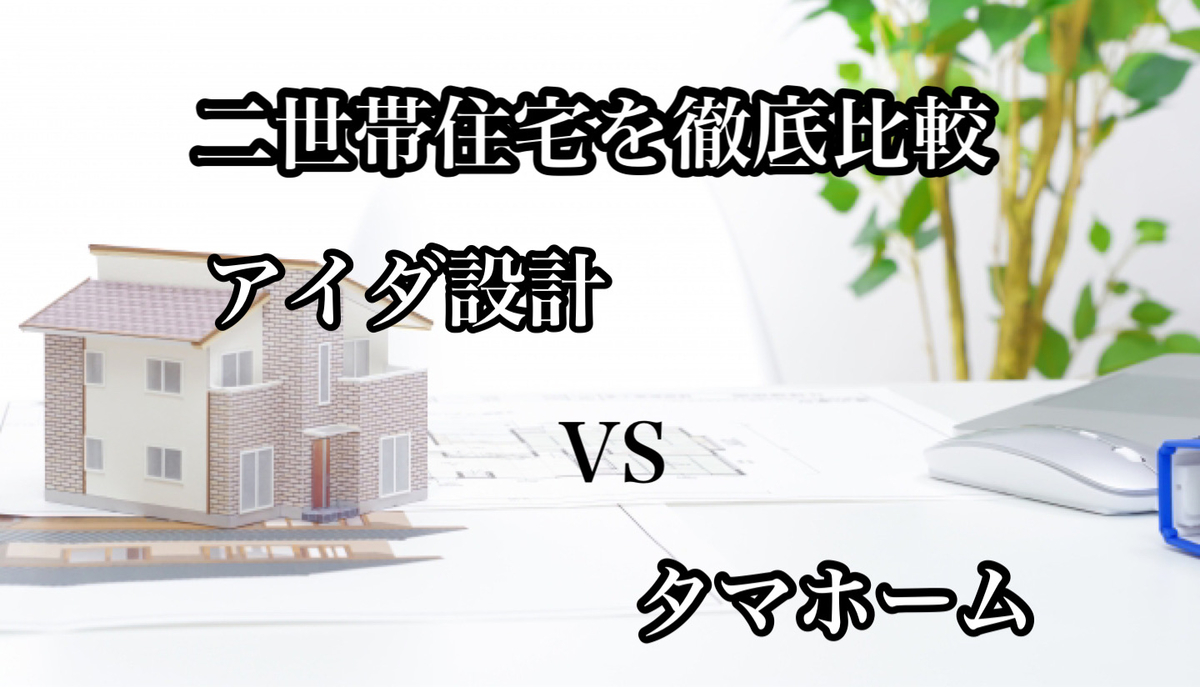この記事を読んで分かること☝
- 新築価格を抑える方法
- ハウスメーカーから相見積を取る際のコツ
- 「プランの比較」と「相見積の比較」の違い
ハウスメーカーを選ぶ際、昨今の値上げ事情もあり、複数のハウスメーカーから相見積を取って比較される方が増加しています。
家電や家具と違い、家の場合は金額が大きいので、極端な話、何百万円もの差があるかもしれません。ただ、家の場合、相見積を取って比較するといっても家電や家具のように簡単ではありません。
家電や家具の場合は、同じメーカーのもので価格比較をできますし、仮にメーカーが違ったとしても金額がそれほど大きくないため、機能・価格の比較はしやすいです。
一方、家の場合、仮に「延床面積30坪のZEH住宅の見積がほしい」と複数のハウスメーカーへ依頼するとプランや見積は提示されますが、各ハウスメーカー毎に条件が違い過ぎるため、本来の相見積の役割を果たせないです。
要するに「実際のところ、どのハウスメーカーの家が安いのか分からない」という状況に陥ってしまいます。単純に金額だけで比較できないのが、ハウスメーカー選びの難しいところですね。
相見積の本来の目的は、同じ条件で見積を作成してもらい価格比較することです。
- 延床面積
- 間取り
- 気密性・断熱性
- 仕様(外壁・設備・床材など)
- 保証(何年保証か)
これらの条件が整っていないと、そもそもの条件が違ってしまうので、相見積というよりは、プランの比較になってしまいます。

新築を検討するうえで大切なことは「プランの比較」と「相見積の比較」をきちんと使い分けることですね。
「プランの比較」では、こちらからの要望は曖昧でも良いです。ハウスメーカーが考えて提案することなので。でも「相見積の比較」の場合は、詳細の条件を伝えたうえで、見積を作成してもらう必要があります。
相見積の比較とは、各ハウスメーカーに同じ条件で見積を作成してもらい金額を比較することです。
この記事では、相見積を取る際のポイントを解説していますので、これから新築をご検討の方は、ぜひ、最後まで読んでみてください。
2012年にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を新築。
二世帯住宅での生活(生活歴10年)しながら、最もローコストで理想の二世帯住宅が、どういうものなのか研究。
実際にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てた経験とその後の生活の経験を活かし、二世帯住宅の情報を発信中。
一男一女の父親。
- 新築の検討で一番問題になるのは価格
- 「プランの比較」と「相見積」は違う
- 得する「相見積」は細かい条件設定が必要
- ハウスメーカーの選定は、「プランの比較」⇒「相見積の比較」
- 「価格」が同レベルなら何でハウスメーカーを選ぶのか
- うまく「相見積」を利用して新築費用を抑える
新築の検討で一番問題になるのは価格
新築の検討を進めていく中で何かと気になるのが予算です。私もたくさんのハウスメーカーを検討しましたが、営業マンから色々な提案を受けて「結局、いくらなんですか?」という質問を何回もしました。
いくら良い提案を受けても予算が足りないことには新築することができません。
下のグラフは、おうちパレットさんの「家を建てる際に不安なことは?」のアンケート結果です。

このアンケート結果でも分かる通り、予算を気にされる方が圧倒的に多いです。
「プランの比較」と「相見積」は違う

新築を検討する時、最近は複数のハウスメーカーから見積を取られる方が多くなっています。
私も家を新築する際、「できるだけ価格を抑えて完全分離型の二世帯住宅を建てたい」という依頼内容でハウスメーカー3社から見積を取りました。
その結果
- A社:延床面積50坪(見積価格3,300万円 ※坪単価66万円)
- B社:延床面積55坪(見積金額2,600万円 ※坪単価47万円)
- C社:延床面積44坪(見積金額2,200万円 ※坪単価50万円)
という結果でした。この見積を見た私の感想は「どのハウスメーカーが良いのか、どのハウスメーカーが安いのか、よく分からない」ということでした。延床面積の違いはもちろんのこと、仕様している設備や間取りも違うため、価格の比較が難しかったですね。
世間ではよく「相見積を取って」という意見がありますが、我が家の場合は「相見積の比較」ではなく「ハウスメーカーのプランの比較」でしたね。
「プランの比較」自体は大切なことですが、ハウスメーカーを見極めるためには、「相見積で比較」をすることも大切です。
もう一度言いますが、「プランの比較」だと、どのハウスメーカーも良く見えてしまい「どのハウスメーカーが良いのか」本当に分からなくなります。
- 「プランの比較」⇒提案内容の比較のため、価格の比較が難しい(条件が違えば価格も違う)
- 「相見積の比較」⇒見積条件を揃えているので、価格比較ができる
得する「相見積」は細かい条件設定が必要

ハウスメーカーを比較するなら同じ条件で見積を作成してもらう必要があります。要するに見積依頼をする際の条件を細かく指定するということです。
- 延床面積
- 間取り(部屋数)
- 家族構成
- トイレの数
- 勾配天井や吹き抜けの有無
- ZEH仕様の有無
- バルコニーの広さ
- 概算予算
など、見積依頼の内容を詳細に指定すればするほど、相見積として価格しやすい状況になります。特にすべてのハウスメーカーに延床面積を合わせてもらえば、坪単価の比較もできるので、検討がしやすくなります。
漠然とした内容でハウスメーカーに見積依頼をするとハウスメーカー毎に捉え方が大きく違うので、まったく比較にならないことも多々あります。
- ハウスメーカーの営業マンが苦手
- 断ることが苦手
- 相談しながらハウスメーカーへ依頼する内容を考えたい
- 複数のハウスメーカーへ見積依頼をする時間がない
という方は、「家づくりのとびら」の利用がおすすめです。専門のアドバイザーに相談しながら、ハウスメーカーへ見積依頼をする内容を決めることができます。

また、断りたいハウスメーカーへの連絡は、「家づくりのとびら」が代行してくれるので気も楽です。
NTTのグループ会社が運営しているサービスなので、安心して利用できることも大きなポイントです。
ハウスメーカーの選定は、「プランの比較」⇒「相見積の比較」
一般的にハウスメーカーを選ぶ際は、複数のハウスメーカーから「プランの提案」を受けて、その中から1社を選ぶケースが多いですね。
ですが、この選定方法では、お得に家を新築できているとは言いにくいです。
ハウスメーカーの選定に限らず、大きな買い物の場合、複数の業者(3~5社程度)からプランの提案を受けて、その中から2社を選びます。
その2社へ詳細の希望を提示して、同じ条件で見積を作成してもらい価格を比較して安い方に決めます。
ですからハウスメーカー選びの流れは
- 3~5社のハウスメーカーから「プランの提案」を受ける
- その中から2社に絞り込む
- 2社へ対して詳細に見積条件を提示して見積を作成してもらう
- 価格比較して安い方に決める
ということですね。
「価格」が同レベルなら何でハウスメーカーを選ぶのか
価格を抑えて新築するためのハウスメーカー選定方法を説明させていただきましたが、仮に最終的な見積価格が同等な場合、どちらのハウスメーカーを選ぶのか迷いますよね。
- 営業マンの印象
- ハウスメーカーの企業規模
- メンテナンス体制
- ハウスメーカーの雰囲気
など、見積価格が同じならこれらを参考にして結論を出すと思いますが、ハウスメーカーの将来性という部分も加味してはいかがでしょうか。
一般的に家を新築すると何十年もその家で暮らすことになります。不具合があった時の対応や将来的なメンテナンス(防蟻処理や外壁塗装、定期点検など)のことを考えると、そのハウスメーカーの将来性も気になるところです。
(倒産してしまっては、困るので)
決算書では、近い未来の予測は分かりますが、10年後20年後は分かりません。そこで私はハウスメーカーの将来性について、そのハウスメーカーが「リフォーム事業」を持っているかどうかで判断するのが良いと考えています。
【倒産せずに生き残るハウスメーカーの見極め方は⁉】リフォーム事業の有無がポイント - 大器晩成を信じて
簡単に説明すると将来、新築戸建ての引渡し棟数は確実に減少します。
そうなった時、新築事業のみのハウスメーカーは、必ず厳しい状況に立たされるわけですが、「リフォーム事業」が確立されていれば、収益の柱がもう一つあり、新築の需要が減少しても対応できるということですね。
「リフォーム事業」に限らず、事業を多角化した経営をしているハウスメーカーというのがポイントです。
うまく「相見積」を利用して新築費用を抑える

「プランの比較」と「相見積の比較」を意識されている方は少ないと思いますが、建てたあと後悔しないためには、この「プランの比較」と「相見積の比較」を意識して使い分けることが重要です。
ほとんどの方は、この2つを混同してしまっているため、家を建てたあと後悔することが多いです。
「○○メーカーの方が良かったかも」
「○○メーカーの方が安かったかも」
「もっとハウスメーカーを比較してから契約すればよかった」
などなど。
上記でも書かせていただきましたが理想は、3~5社から「プランの提案」を受けて、その中から2社に絞り、そこから「相見積の比較」ですね。
ただ、5社のハウスメーカーへ見積依頼をするのが大変ですし、5社へ見積依頼をするということは、最終的に1社に決めることになるため、4社へ断らなければならないです。
結構な労力を使うため、ここまで行動できない方もいらっしゃいますよね。
そういう方は、「住まいの窓口」や「家づくりのとびら」などの資料請求を利用してみてはいかがでしょうか。
専門のアドバイザーに相談しながら、ハウスメーカーへの依頼内容を決めることができて、その上、ハウスメーカーへのお断りの代行もしてくれます。
- 忙しくてハウスメーカー選びに時間をかけられない
- 新築を検討しているけど、何が良いのか分からない
- 家づくりに関することを誰かに相談しながら進めたい
- ハウスメーカーの営業マンが苦手な方
という方にはおすすめですね。詳しくはこちらの記事をご覧ください。